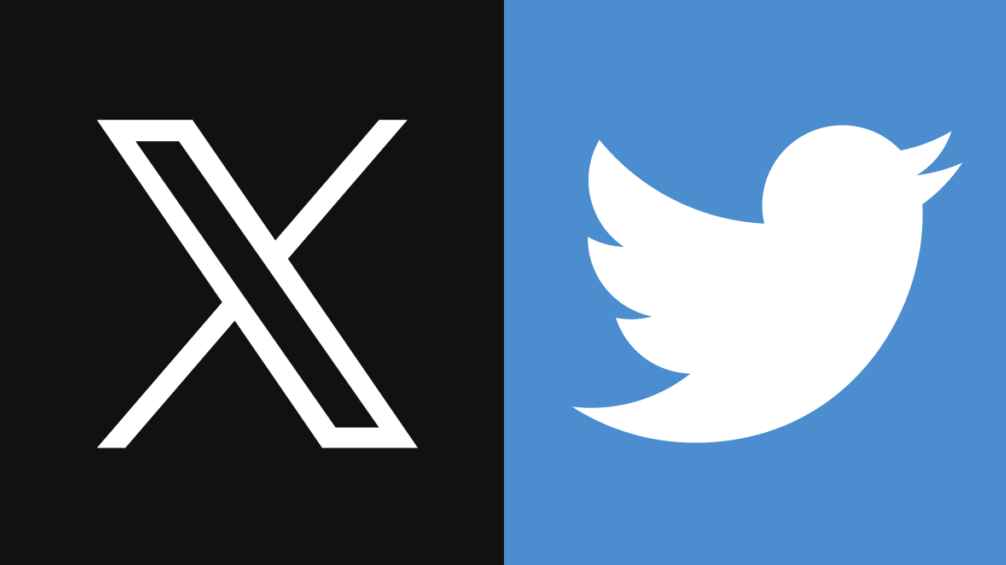最終更新日 2025年9月8日
退職後にすぐ次の職場で働き始める場合、さまざまな手続きが必要です。

この記事では、退職後すぐに就職する際の手続きを、ハローワーク、年金、健康保険、税金などの観点から具体例を交えて詳しく解説します。
退職後すぐに就職する予定の人は、ぜひ参考にしてください。
おすすめの転職エージェントがすぐわかる
⇩⇩
目次
退職後すぐに就職するメリットと準備の重要性
退職後すぐに次の仕事に就く場合、収入の途切れがなく、生活の安定を保ちやすいという大きなメリットがあります。
また、キャリアの空白期間が短いため、履歴書や面接での印象も良くなることが多いです。
しかし、手続きを怠ると、年金や保険の未納、税金の処理ミスなどが発生するリスクが。

例えば、会社を退職し、2週間後に新しい職場で働き始める場合、退職日と入社日の間に年金や健康保険の手続きを済ませる必要があります。
このようなケースでは、スケジュールを事前に立て、必要書類を準備しておくことが成功の鍵です。
以下で、具体的な手続きの流れを順を追って解説します。
また、退職後の流れ完全ガイドも、合わせて参考にしてみてください。
1. 退職時に必要な書類の準備
退職が決まったら、まず会社から受け取るべき書類を確認しましょう。
これらは次の就職先や各種手続きで必要になります。以下は主な書類とその用途です。
✅離職票:
ハローワークでの失業保険手続きや新しい職場での手続きに必要です。
通常、退職後10日前後で発行されますが、会社によっては遅れる場合もあるため、早めに確認しましょう。
✅源泉徴収票:
年末調整や確定申告で必要です。
新しい職場に提出することで、前職の収入を正確に申告できます。
✅年金手帳:
年金関連の手続きで必要になる場合があります。
紛失している場合は、年金事務所で再発行手続きが必要です(手数料無料、1~2週間程度で発行)。
✅健康保険資格喪失証明書:
健康保険の切り替え時に必要です。
退職後に国民健康保険や任意継続の手続きを行う際に提出します新しい職場で健康保険に加入するまでのつなぎとして使います。
✅雇用保険被保険者証:
雇用保険の加入履歴を確認するために必要です。
新しい職場での雇用保険加入時に提出する場合があります。
これらの書類は、退職時に会社に確認して確実に受け取っておきましょう。
書類の準備が遅れると、年金や保険の手続きに影響が出る可能性があります。

事前に会社の人事担当者に発行時期を確認しておくと安心です。
退職手続きについては、以下の記事でさらに詳しく解説👇
2. ハローワークでの手続き
退職後すぐに就職する場合でも、ハローワークでの手続きが必要なケースがあります。
特に、失業保険の受給資格を確認したい場合や、職業訓練の情報を得たい場合は早めに訪問しましょう。
ハローワークは全国にあり、求職者向けのサポートが充実しています。
ハローワークで必要な手続き
✅離職票の提出:
離職票を提出することで、失業保険の受給資格を確認できます。
ただし、すぐに就職する場合は受給の必要がない場合がほとんどです。
それでも、離職票は他の手続きで必要になることがあるため、必ず受け取っておきましょう。
✅求職登録:
次の職場が決まっていない場合、求職登録をすることで求人情報を得られます。
すぐに就職する場合はこの手続きは不要です。
✅職業訓練の相談:
スキルアップを目指す場合、職業訓練受講給付金や無料の訓練コースの情報を得られます。
例えば、ITスキルや簿記などの資格取得を目指す場合、職業訓練は有効な選択肢です。
ハローワークは平日の日中が混雑するため、事前にオンラインで予約するか、必要書類を公式サイトで確認しておくと効率的です。

また、ハローワークでは無料の転職相談も行っているため、転職に不安がある場合は利用してみましょう。
3. 年金の手続き
退職後すぐに就職する場合、年金の手続きは特に重要です。
国民年金と厚生年金の切り替えが発生する可能性があり、適切な手続きを行わないと将来の年金受給額に影響が出るリスクが。
以下に、具体的な手続きの流れを解説します。
国民年金から厚生年金への切り替え
退職後、国民年金に一時的に加入する場合がありますが、新しい職場で厚生年金に加入する場合は速やかに切り替えが必要です。
以下は一般的な手続きの流れです。
✅退職時に年金手帳を確認:
年金手帳を準備し、必要に応じて新しい職場に提出。
紛失している場合は、年金事務所や市区町村役場で再発行手続きを行います。
マイナンバーカードがあれば、年金手帳の代わりにマイナンバーを提出できる場合も。
✅国民年金の加入手続き:
退職後14日以内に市区町村役場で国民年金への加入手続きを行います。
保険料は月額約1万7000円(2025年度の場合)で、口座振替やクレジットカード払いも可能です。
ただし、すぐに就職する場合は新しい職場が厚生年金の加入手続きを行うため、国民年金の加入期間が短くなるか、不要になる場合があります。
✅厚生年金の加入:
新しい職場で厚生年金に加入する場合は、会社が手続きを行います。
入社時に年金手帳やマイナンバーを提出し、加入手続きをスムーズに進めましょう。
厚生年金は給与から天引きされるため、保険料の支払い漏れの心配はありません。
例えば、前職を3月31日に退職し、4月15日に入社する場合、退職から入社までの約2週間は国民年金に加入する必要があります。
しかし、新しい職場が4月1日から厚生年金の手続きを進める場合、国民年金の加入手続きを省略できることも。
このようなケースでは、事前に新しい職場の担当者に確認しておくと安心です。

年金事務所や市区町村役場の窓口では、無料で相談に応じているので相談してみるのもおすすめ。
また、日本年金機構の公式サイトでは、スマホから年金記録の確認や手続きの詳細をチェックできます。
4. 健康保険の手続き
健康保険の切り替えも、退職後すぐに就職する際に欠かせない手続きです。
保険証がない期間が発生すると、医療機関での受診が全額自己負担になるため、注意が必要です。
以下に、健康保険の手続きの選択肢と流れを解説します。
健康保険の選択肢
✅国民健康保険への加入:
退職後、新しい職場で健康保険に加入するまでの間、国民健康保険に加入する必要があります。
市区町村役場で手続きを行い、保険料は前年度の所得に基づいて計算されます(月額2~5万円程度が目安)。
必要書類は健康保険資格喪失証明書、身分証明書、マイナンバーなどです。
✅任意継続被保険者制度:
前の職場の健康保険を最長2年間継続できる制度です。
保険料は会社負担分を含めて全額自己負担(月額2~4万円程度)となり、国民健康保険より安い場合もあります。
退職後20日以内に手続きが必要です。
✅新しい職場の健康保険:
新しい職場で健康保険に加入する場合は、会社が手続きを行います。
入社時に健康保険資格喪失証明書や身分証明書を提出しましょう。
加入手続きは通常、入社後1週間以内に完了します。
例えば、退職後すぐに就職する場合、4月1日に入社するなら新しい職場の健康保険に即日加入できる可能性があります。
しかし、入社日が4月15日の場合、4月1日から14日までの間は国民健康保険に加入するか、任意継続を選択しなければなりません。
保険証がない状態で病院を受診すると、医療費の全額(例えば、風邪の診察で1万円程度)を自己負担することになるため、早めの手続きが重要です。

市区町村役場の窓口や健康保険組合のウェブサイトで詳細を確認し、必要書類を準備しておきましょう。
スマホでオンライン申請が可能な自治体も増えているため、事前に確認すると便利です。
5. 税金関連の手続き
退職後すぐに就職する場合、税金に関する手続きも忘れずに行いましょう。
源泉徴収票の提出や年末調整、確定申告など、正確な手続きが求められます。
以下に、具体的なポイントを解説します。
税金の手続きのポイント
✅源泉徴収票の提出:
新しい職場で年末調整を行うために、前職の源泉徴収票を提出します。
源泉徴収票には前職での給与や源泉徴収された税額が記載されており、正確な税金の計算に必要です。
通常、退職後1~2週間で発行されます。
✅年末調整:
新しい職場で年末調整を行う場合、前職の収入も含めて計算されます。
源泉徴収票を提出期限(通常12月上旬)までに提出しないと、年末調整が受けられず、確定申告が必要になるケーズも。
✅確定申告:
退職した年や新しい職場で年末調整が間に合わない場合、確定申告が必要になることがあります。
例えば、3月に退職し、4月から新しい職場で働き始めた場合、前職と現職の収入を合算して確定申告を行うことで、過払い分の税金が還付されることも。
e-Taxを利用すると、スマホやパソコンから簡単に申告できます(提出期限は翌年3月15日)。
税金の手続きを怠ると、還付金を受け取れなかったり、追加の納税が発生したりするリスクが。
例えば、源泉徴収票を紛失した場合、前の職場に再発行を依頼する必要があります。

また、国税庁の公式サイトでは、スマホで確定申告のシミュレーションや必要書類の確認が可能です。
6. その他の手続きと注意点
退職後すぐに就職する場合、年金や保険以外の細かな手続きも必要になる場合があります。
以下に、状況に応じて確認すべきポイントをまとめました。
✅住民税:
退職時に住民税の支払い方法(一括または分割)を確認します。
新しい職場で給与から天引きされる場合もありますが、退職時期によっては一括納付を求められることがあります(例えば、6月退職の場合、残りの年度分の住民税を一括で支払うケース)。
市区町村役場で支払い方法を確認しましょう。
✅雇用保険:
新しい職場で雇用保険に加入する手続きは、会社が行います。
雇用保険被保険者番号を確認し、入社時に提出するとスムーズです。
雇用保険は失業時の給付だけでなく、育児休業給付金などにも関わるため、加入状況を把握しておきましょう。
✅有給休暇の消化:
退職前に有給休暇を消化する場合、退職日を調整して手続きを進めます。
例えば、20日の有給休暇を保有している場合、退職日を遅らせて有給を消化することで、収入の空白期間を減らせるケースも。
✅退職金の確認:
前職で退職金制度がある場合、支払い時期や金額を確認しましょう。
退職金は確定申告の対象になる場合があるため、源泉徴収票と併せて管理します。
これらの手続きは、退職日や入社日に合わせて計画的に進めることが重要です。
カレンダーアプリやメモを活用して、スケジュールを整理しておくと漏れが防げます。
また、不明点があれば、各機関の公式サイトや窓口で確認しましょう。
スムーズな転職のための準備
退職後すぐに就職する場合、手続きだけでなく、新しい職場でのスタートを成功させるための準備も大切です。
以下に、具体的な準備のポイントを紹介します。
✅必要書類の確認:
入社時に必要な書類(履歴書、職務経歴書、身分証明書、マイナンバーなど)を事前に確認し、準備しておきましょう。
会社によっては、銀行口座情報や通勤経路の申告も求められる場合があります。
✅職場のルール確認:
新しい職場の就業規則や社内ルール、ドレスコードを事前に確認しておくと、初日からスムーズに業務を始められます。
例えば、IT企業ではカジュアルな服装が許可される場合が多いですが、事前に確認しておくと安心です。
✅メンタルケア:
転職は新しい環境への適応が求められるため、精神的な負担が大きい場合があります。
退職前に十分な休息を取ったり、信頼できる人に相談したりして、メンタル面の準備を整えましょう。
瞑想アプリや運動を取り入れるのも効果的です。
✅業界情報のアップデート:
新しい職場の業界や業務内容に関する最新情報を調べておくと、初日から積極的に貢献できます。
例えば、マーケティング職に転職する場合、最新のデジタル広告トレンドをチェックしておくと有利です。
新しい職場での成功は、事前準備にかかっています。
手続きと並行して、気持ちや知識の準備も進めましょう。
よくある質問とその回答
退職後すぐに就職する際によくある質問をまとめました。
これらを参考に、不明点を解消してください。
Q1. 退職後すぐに就職する場合、失業保険は受け取れますか?
A. 退職後すぐに就職する場合、失業保険の受給対象外となることが一般的です。
失業保険は「失業状態」にあることが条件のため、就職が決まっている場合は受給できません。
ただし、離職票はハローワークでの手続きや確認のために必要なので、必ず受け取りましょう。
失業保険受給中に就職が決まった場合は、以下の記事で解説👇
Q2. 健康保険の切り替えに期限はありますか?
A. 退職後、国民健康保険への加入や任意継続の手続きは14日以内に行う必要があります。
新しい職場で健康保険に加入する場合は、入社時に速やかに手続きを進めましょう。
保険証がない期間を防ぐため、早めの行動が重要です。
Q3. 年末調整はどうなりますか?
A. 新しい職場で年末調整を行う場合、前職の源泉徴収票を提出する必要があります。
提出が遅れると、年末調整が受けられず、確定申告が必要になる場合があるので注意。
12月上旬までに提出できるよう、準備しておきましょう。
Q4. 国民年金の保険料を払う必要はありますか?
A. 退職から入社までの期間が短い場合、国民年金の加入手続きが不要な場合があります。
新しい職場で厚生年金に加入するタイミングを確認し、年金事務所や市区町村役場で相談すると確実です。
Q5. 転職先で必要な書類は何ですか?
A. 転職先で一般的に必要な書類は、履歴書、職務経歴書、身分証明書、マイナンバー、源泉徴収票、年金手帳、雇用保険被保険者証などです。
会社によって異なるため、事前に採用担当者に確認しましょう。
大手人気企業へのキャリアアップなら、シンシアードが最適!

シンシアードは、DX・マーケティング・営業などのハイクラス求人に特化した転職エージェントです。
リクルート出身のプロコンサルタントが、非公開求人を紹介し、年収1000万円超の実績も多数!
面接対策から条件交渉まで全力サポートで、理想の転職ができますので、ぜひこの機会に相談してみてください。
\無料登録はコチラ/
まとめ:スムーズな転職のために
退職後すぐに就職する場合、離職票や源泉徴収票の準備、年金や健康保険の切り替え、税金の手続きなど、さまざまな手続きが必要です。
これらをスムーズに進めるためには、退職前からスケジュールを立て、必要書類を整理しておくことが大切。
ハローワークや市区町村役場、税務署を活用し、不明点は早めに解消しましょう。
また、シンシアードはハイクラスへの理想の転職ができますので、ぜひこの機会に相談してみてください。
\無料登録はコチラ/