最終更新日 2025年6月7日
会社を辞める際、どのように伝えるかは非常に重要です。
適切な言い方を選べば、円満退職が可能になり、将来のキャリアにも良い影響を与えます。
この記事では、個人ブログならではの視点で、会社を辞める時の言い方や伝え方のコツを詳しく解説します。
退職のタイミングから上司への伝え方、具体的な例文、さらには退職後に気をつけるべきことまで、私の経験や周囲の話を交えてお伝えします。
退職を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

あなたの希望や強みを分析し、最適な転職エージェントを紹介!
\無料カウンセリングはコチラ/
オンライン面談無料、20代の転職活動を最適なエージェントで解決!
目次
会社を辞める前に考えるべきこと
退職を決意する前に、準備を整えておくと、話がスムーズに進みます。
以下に、退職前に考えるべきポイントを詳しくまとめました。
1. 退職の理由を明確にする
なぜ会社を辞めたいのか、理由を明確にしましょう。
キャリアアップ、職場環境の不満、プライベートの事情など、理由は人それぞれです。
明確な理由があれば、上司に伝える際も説得力が増し、話がブレません。
例えば、「新しい業界でスキルを磨きたい」「家庭の時間を優先したい」など、ポジティブかつ具体的な理由を準備しておくと良いでしょう。
理由が曖昧だと、上司から引き止められやすくなるので注意が必要です。
2. 退職のタイミングを考える
退職のタイミングは、会社の繁忙期やプロジェクトの進行状況を考慮して決めましょう。
一般的には、退職の1〜2ヶ月前に伝えるのがマナーとされています。
民法では2週間前の通知で良いとされていますが、就業規則を確認し、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
例えば、年度末や大型プロジェクトの直前は避け、業務に影響が少ない時期を選ぶと、会社への配慮が伝わります。
タイミングを間違えると、退職の印象が悪くなる可能性があるので慎重に。
3. 次のキャリアプランを考える
辞めた後のプランが明確だと、退職の意思を伝えやすくなります。
転職、独立、留学など、具体的な目標があると、上司や同僚にも納得感を与えられます。
プランが決まっていなくても、「自分を見つめ直す時間を持ちたい」「新たな挑戦に向けて準備したい」といった前向きな言い回しを準備しましょう。
次のステップが曖昧だと、「本当に辞める必要があるのか?」と質問される可能性があるので、ある程度の方向性を示せるようにしておくのがおすすめです。
4. 経済的な準備を確認する
退職後の生活を支える資金計画も重要です。
次の仕事が決まるまでの生活費や、失業保険の受給条件などを事前に確認しておきましょう。
貯金の目安としては、3〜6ヶ月分の生活費を準備しておくと安心です。
また、退職後の健康保険や年金の手続きも忘れずに行いましょう。
これらの準備を怠ると、退職後に慌てることになるので、早めにチェックしておくのが賢明です。
会社を辞める時の適切な言い方
退職の意思を伝える際、どのように話すかが円満退職のカギを握ります。
以下に、具体的な伝え方のポイントを詳しく紹介します。
1. 直属の上司にまず伝える
退職の話は、まず直属の上司に伝えるのが基本です。
同僚や他の部署に先に話すと、情報が漏れてトラブルの原因になることがあります。
上司との1対1の面談を設定し、落ち着いた環境で話すようにしましょう。
面談の際は、事前にアポイントを取り、「個人的な相談があります」と伝えておくとスムーズです。
メールや電話ではなく、直接話すのがベストですが、リモートワークの場合はビデオ会議でも問題ありません。
2. ポジティブな表現を使う
退職理由を伝える際、ネガティブな表現は避けましょう。
例えば、「職場の人間関係が嫌だから」ではなく、「新しい挑戦をしたいと思ったから」と伝える方が印象が良くなります。
感謝の気持ちを添えると、さらに好印象です。
具体例として、「この会社で学んだことを活かして、次のステップに進みたい」「〇〇部長のご指導のおかげで成長できたので、新たな目標に挑戦したい」と伝えると、誠意が伝わります。
3. 具体的な退職時期を提案する
退職の意思を伝える際、具体的な退職時期を提案しましょう。
例えば、「3月末での退職を考えていますが、引き継ぎの都合で調整可能です」と伝えると、誠実さが伝わります。
会社の状況を考慮し、柔軟な姿勢を見せることで、円満な退職に繋がります。
もし上司から「もう少し残ってほしい」と言われた場合、引き継ぎの期間を明確に提案することで、話がスムーズに進みます。
4. 感謝の気持ちを強調する
退職の話をする際、会社や上司、同僚への感謝の気持ちを必ず伝えましょう。
「〇〇年間、本当に多くのことを学べました」「チームのサポートがあって成長できました」など、具体的なエピソードを交えると効果的です。
感謝を伝えることで、退職後も良い関係を維持しやすくなり、将来の推薦状や人脈にも繋がる可能性があります。
退職の伝え方の具体例
ここでは、退職の意思を伝える際の具体的な例文をシチュエーション別に紹介します。
状況に応じてアレンジしてください。
例文1:キャリアアップを理由に退職する場合
「〇〇部長、お時間をいただきありがとうございます。実は、かねてより興味のあった〇〇の分野で新たな挑戦をしたいと考え、退職を決意しました。これまで〇〇年間、この会社で多くのことを学び、〇〇部長のご指導にも心から感謝しています。退職は〇月末を予定していますが、引き継ぎの都合を考慮し、調整可能です。どうぞよろしくお願いいたします。」
この例文は、感謝の気持ちと前向きな理由を強調し、柔軟な姿勢を示しています。
キャリアアップの理由は、上司にも納得されやすい傾向があります。
例文2:プライベートの事情で退職する場合
「〇〇課長、お忙しいところ恐縮です。私事ではありますが、家庭の事情により、フルタイムでの勤務が難しくなり、退職を決意しました。これまで支えてくれて本当にありがとうございました。〇〇課長のアドバイスのおかげで、多くのことを学べました。退職は〇月を予定していますが、引き継ぎや業務の調整はしっかり行います。よろしくお願いします。」
プライベートな理由でも、簡潔かつ誠意を持って伝えることで、理解を得やすくなります。
感謝の具体例を入れると、より温かみのある印象に。
例文3:まだ次のプランが決まっていない場合
「〇〇部長、お時間をいただきありがとうございます。自分自身のキャリアを見直すため、一旦退職を決意しました。この会社での経験は私の財産であり、〇〇部長やチームの皆さんに心から感謝しています。退職は〇月末を考えていますが、引き継ぎは責任を持って行います。どうぞよろしくお願いします。」
プランが未定でも、前向きな姿勢と感謝を伝えることで、誠実な印象を与えられます。
曖昧すぎないよう、「見直す」などの言葉で方向性を示しています。
例文4:人間関係や職場環境が理由の場合
「〇〇課長、お時間ありがとうございます。自分自身のキャリアや働き方を見つめ直したいと考え、退職を決意しました。この会社で〇〇年間、様々なプロジェクトに携われたこと、課長のご指導を受けられたことに感謝しています。退職は〇月末を予定していますが、引き継ぎは丁寧に行います。よろしくお願いいたします。」
人間関係や環境が理由でも、直接的な不満は避け、前向きな表現に変換。
感謝と引き継ぎの誠意を強調することで、角を立てずに伝えられます。

あなたの希望や強みを分析し、最適な転職エージェントを紹介!
\無料カウンセリングはコチラ/
オンライン面談無料、20代の転職活動を最適なエージェントで解決!
退職を伝えた後に気をつけること
退職の意思を伝えた後も、円満退職のために気をつけるべきポイントがあります。
以下に、具体的な注意点を詳しく解説します。
1. 引き継ぎを丁寧に行う
退職が決まったら、業務の引き継ぎを丁寧に行いましょう。
引き継ぎ資料を作成し、後任者や同僚に分かりやすく説明することが大切です。
進行中のプロジェクトやクライアント対応がある場合は、細かく情報を共有しておくと、会社への迷惑を最小限に抑えられます。
例えば、業務マニュアルや連絡先リスト、進行中のタスクの進捗状況を整理し、誰が見ても分かる状態にしておきましょう。
引き継ぎがスムーズだと、最後の印象も良くなります。
2. 同僚や関係者に感謝を伝える
退職前に、同僚や関係者に感謝の気持ちを伝えましょう。
直接話すのが難しい場合は、メールや手紙で伝えるのも良い方法です。
「一緒に働けて楽しかった」「サポートしてくれてありがとう」といった言葉を添えると、良い関係を保ったまま退職できます。
特に、親しい同僚には個別にメッセージを送ると、退職後も人脈として繋がりやすくなります。
感謝の気持ちは、将来のキャリアにもプラスに働きます。
3. 退職日まで責任感を持って働く
退職が決まったからといって、仕事の手を抜くのはNGです。
最後まで責任感を持って働くことで、良い印象を残せます。
特に、最後の数週間は周囲の目が気になるもの。普段以上に丁寧な対応を心がけましょう。
例えば、クライアントへの対応やチームのサポートを積極的に行うことで、「最後までプロフェッショナルだった」と評価される可能性が高まります。
4. 退職後の連絡先を共有する
退職後も関係を維持したい同僚や上司には、プライベートの連絡先(メールやSNS)を共有しておくと良いでしょう。
ただし、必要以上に連絡先を広めるのは避け、信頼できる人に限定するのが賢明です。
連絡先を共有する際は、「今後も何かあればご連絡ください」といった軽い一言を添えると、自然な印象になります。
よくある質問:会社を辞める時の言い方
退職に関するよくある質問とその回答をまとめました。
実際の悩みに基づいた内容で、参考にしてください。
Q1. 退職の話を切り出すタイミングは?
A. 上司の忙しい時期を避け、落ち着いたタイミングを選びましょう。
週初めの午前中や、プロジェクトの区切りがついた時がおすすめです。
事前に面談の時間を予約し、1対1で話せる環境を整えると良いでしょう。
例えば、「来週の月曜日の午前中に30分ほどお時間いただけますか?」と事前に打診すると、スムーズに話が進みます。
Q2. 上司が引き止めてきたらどうする?
A. 引き止められた場合、まずは感謝の気持ちを伝えつつ、退職の意思が固いことを丁寧に伝えましょう。
「せっかくのお言葉ですが、自分のキャリアを考え、この決断に至りました」と伝えるのが効果的です。
曖昧な態度を取ると話が長引くので、明確に意思を伝えることが大切。
必要なら、「〇月末までは責任を持って働きます」と期間を区切って伝えると良いでしょう。
Q3. 退職理由を正直に話すべき?
A. 必ずしも全てを正直に話す必要はありません。
ネガティブな理由(例:上司と合わない)は、ポジティブな言い換えを考えると良いでしょう。
例えば、「人間関係が辛い」→「新しい環境でスキルを磨きたい」と伝えると、角が立ちません。
正直に話す場合も、感情的にならず、事実を冷静に伝えることが大切です。
過度な不満は避け、建設的な姿勢を心がけましょう。
Q4. 退職をメールで伝えてもいい?
A. 基本的には直接話すのがマナーですが、リモートワークや物理的な距離がある場合は、メールやビデオ会議でも問題ありません。
ただし、メールの場合は丁寧な文面を心がけ、事後に電話や面談でフォローすることをおすすめします。
メールの例:「〇〇部長、いつもお世話になっております。個人的な相談があり、〇月〇日にオンラインでお時間をいただけないでしょうか。退職についてお話ししたいと考えています。」
円満退職のための追加のコツ
さらに円満退職を確実にするために、以下のコツも押さえておきましょう。
これらは、私や友人の実体験から得た教訓です。
1. 退職願・退職届の書き方を確認する
退職の意思を伝えた後、正式な退職願や退職届を提出する必要があります。
会社によっては指定のフォーマットがあるので、事前に人事部や就業規則を確認しましょう。
一般的な書き方は以下の通りです。
- 「退職願」または「退職届」とタイトルを記載。
- 提出先(社長や人事部長の名前)を明記。
- 退職日(例:〇年〇月〇日)を具体的に書く。
- 簡潔な理由(例:「一身上の都合により」)を記載。
- 自分の名前と提出日を記入。
例:「退職願 〇〇株式会社 代表取締役社長 〇〇様 一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたします。〇年〇月〇日 〇〇(氏名)」
2. 会社のルールを再確認する
退職に関するルールは、就業規則に記載されています。
通知期間(1ヶ月前など)、有給休暇の消化ルール、競業避止義務などを確認しましょう。
特に、有給休暇は退職前に消化できる場合が多いので、早めに申請しておくと良いでしょう。
ルールを守ることで、会社とのトラブルを回避し、円満退職に繋がります。
疑問点があれば、人事部に直接確認するのが確実です。
3. 退職後のネットワークを意識する
退職後も、元同僚や上司との関係はキャリアの資産になります。
退職前に、信頼できる人たちと連絡先を交換したり、LinkedInで繋がったりしておくと良いでしょう。
例えば、退職の挨拶メールに「今後も何かあればご連絡ください」と一言添えるだけで、関係を維持しやすくなります。
将来の転職や仕事の紹介に繋がる可能性も。

あなたの希望や強みを分析し、最適な転職エージェントを紹介!
\無料カウンセリングはコチラ/
オンライン面談無料、20代の転職活動を最適なエージェントで解決!
まとめ:円満退職を目指して適切な言い方を
会社を辞める時の言い方は、円満退職のために非常に重要です。
退職の理由を明確にし、適切なタイミングで上司に伝え、感謝の気持ちを忘れずに話すことがポイントです。
この記事では、具体的な例文や注意点、よくある質問、追加のコツまで詳しく紹介しました。
退職は新たなスタートの第一歩。誠実な態度で進めることで、良い関係を保ちながら次のステップに進めるはずです。
もし退職の伝え方で迷っているなら、この記事を参考に、自信を持って一歩を踏み出してください。応援しています!














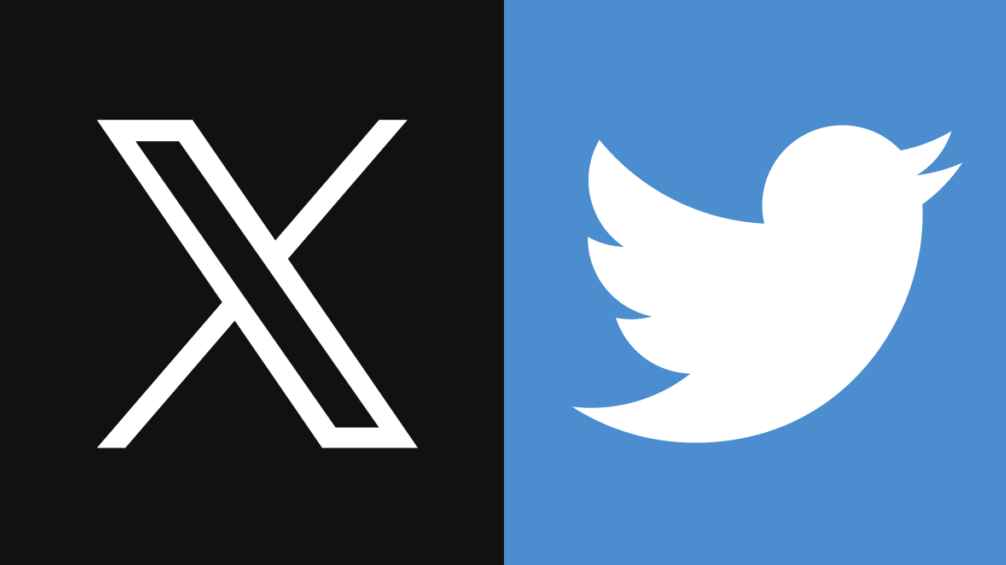

コメントを残す