最終更新日 2025年6月7日
新しい職場での試用期間中、「この仕事、合わないかも…」と感じて辞めたいと思うことは珍しくありません。
試用期間は企業と従業員がお互いの適性を見極める期間ですが、そこで「辞めたい」と感じるのは自然なことです。
しかし、試用期間中の退職には正社員とは異なるルールや注意点があります。
この記事では、試用期間中に辞めたいと思ったときの対処法、法律上のポイント、手続きの流れ、円満退職のコツ、そして次のステップに向けたアドバイスをわかりやすく解説します。

あなたの希望や強みを分析し、最適な転職エージェントを紹介!
\無料カウンセリングはコチラ/
オンライン面談無料、20代の転職活動を最適なエージェントで解決!
目次
試用期間とは?辞めたいと思う前に知っておきたい基礎知識
試用期間とは、企業が新入社員の能力や適性、職場への適合度を見極めるために設ける期間のことです。
通常、3ヶ月から6ヶ月、場合によっては1年程度設定されることもあります。
試用期間中は正社員と比べて労働条件(給与や福利厚生)が異なる場合があり、雇用契約書や就業規則でその詳細が定められています。
試用期間中に辞めたいと感じる理由は人によって異なりますが、以下のようなケースが一般的です。
- 仕事内容が求人情報や面接時の説明と異なる
- 職場の人間関係や雰囲気が合わない
- 給与や残業時間などの労働条件に不満がある
- 自分のスキルやキャリアビジョンと合わない
- 精神的なストレスやプレッシャーが大きい
こうした理由で辞めたいと思うのは、決してあなたが「我慢不足」なわけではありません。
試用期間は企業だけでなく、労働者にとっても職場を見極める大切な期間です。
辞めることを考える前に、まずは自分の気持ちや状況を整理し、冷静に次のステップを考えることが重要です。
試用期間中に辞めたいと感じる理由を深掘りしよう
辞めたいという気持ちが漠然としている場合、具体的な理由を整理することで、退職すべきか、続けるべきかの判断がしやすくなります。
以下では、試用期間中に辞めたいと感じる主な理由と、それぞれの対処法を詳しく解説します。
1. 仕事内容がイメージと異なる場合
求人票や面接で聞いていた仕事内容と実際の業務が大きく異なるケースは少なくありません。
例えば、「企画やクリエイティブな仕事が中心」と聞いていたのに、実際はデータ入力や雑務が主だった、というケースです。
このようなギャップはモチベーションの低下につながります。
対処法:まずは上司や人事に率直に相談し、業務内容の調整が可能か確認しましょう。試用期間中は企業側も柔軟に対応してくれる場合があります。
例えば、希望する業務に少しずつ関われるよう交渉するのも一つの方法です。
相談しても状況が変わらない場合や、業務内容が自分のキャリア目標と合わない場合は、退職を検討するのも合理的な選択です。
2. 職場の人間関係や雰囲気が合わない
新しい職場では人間関係を構築するのに時間がかかりますが、試用期間中に「この職場の雰囲気は自分に合わない」と感じることがあります。
上司のマネジメントスタイルや同僚とのコミュニケーションがストレスになる場合も多いです。
対処法:特定の人物との関係が問題なら、距離を置く工夫や他の社員との交流を増やすことで改善する場合があります。
また、職場の文化や価値観が合わないと感じる場合は、試用期間中にその違和感をしっかり観察しましょう。
長期的に働き続けるのが難しいと感じるなら、早めに次のステップを考えるのも賢明です。
3. 労働条件に不満がある
給与が低い、残業が多い、休日が少ない、福利厚生が不十分など、労働条件が期待と異なる場合も辞めたい理由になります。
特に、求人票に記載されていた条件と実際が異なる場合は、信頼感が揺らぎます。
対処法:まずは労働契約書や就業規則を確認し、条件が契約内容と異なる場合は人事に相談しましょう。
もし違法性(最低賃金以下や過度な残業など)が疑われる場合は、労働基準監督署や労働組合に相談するのも有効です。
条件が改善されない場合、退職を視野に入れるのも一つの選択肢です。
4. スキルやキャリアビジョンとのミスマッチ
試用期間中に「この仕事では自分のスキルが活かせない」「将来のキャリアビジョンに合わない」と感じることもあります。
例えば、専門性を高めたいのに、業務が単純作業ばかりで成長が見込めない場合などです。
対処法:自分のキャリア目標を再確認し、現在の職場でそれが実現可能かを見極めましょう。上司にキャリアパスの相談をするのも有効です。
もし長期的な成長が難しいと感じるなら、転職を視野に入れ、試用期間中に次の仕事を探し始めるのも良いでしょう。
試用期間中の退職と法律:知っておきたいルール
試用期間中の退職には、正社員とは異なるルールが適用される場合があります。
以下に、法律的なポイントを詳しく解説します。
試用期間中の解雇と退職の違い
試用期間中は、企業側が「適性がない」と判断した場合、解雇される可能性があります。
一方、退職は労働者自らが辞める意思を表明する行為です。
日本では労働者の退職の自由が民法627条で保障されており、試用期間中でも原則として自由に退職できます。
ただし、試用期間中の解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。
もし不当解雇と感じる場合は、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
退職の申し出はいつすればいい?
民法では、退職の2週間前に申し出れば退職可能とされています。
ただし、就業規則で「1ヶ月前までに通知」など異なる期間が定められている場合、そちらが優先されることがあります。
試用期間中は企業側も比較的柔軟に対応してくれるケースが多いので、就業規則を確認し、早めに上司に相談するのがベストです。
例えば、「〇月〇日までに退職したい」と具体的な日付を伝え、引き継ぎや後任の準備期間を考慮すると、円満退職につながります。
有給休暇や退職金の扱いは?
試用期間中は入社間もないため、有給休暇が発生していない場合がほとんどです。
また、退職金も試用期間中の退職では支給されないのが一般的です。
ただし、企業によっては独自のルールを設けている場合があるので、労働契約書や就業規則を確認しましょう。
もし不明点があれば、人事部に直接問い合わせることをおすすめします。
試用期間中の退職と失業保険
試用期間中に退職した場合、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給資格が気になる方も多いでしょう。
失業保険を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入していた期間が通算12ヶ月以上(特定受給資格者の場合は6ヶ月以上)
- 自己都合ではなく会社都合の退職である場合(試用期間中の解雇など)
- ハローワークで求職活動を行う意思がある
試用期間が短い場合、雇用保険の加入期間が足りず受給できないケースも多いです。
自己都合退職の場合、給付制限期間(2〜3ヶ月)が設けられることもあります。
詳細は最寄りのハローワークで確認してください。
試用期間中に辞める際の具体的な手続き
辞めたい気持ちが固まったら、円満退職を目指して以下の手続きを進めましょう。
スムーズな退職は、次のキャリアにも良い影響を与えます。
1. 退職の意思を上司に伝える
まずは直属の上司に退職の意思を口頭で伝えましょう。
メールや書面で突然伝えるよりも、直接話す方が誠意が伝わり、トラブルを避けられます。
以下のポイントを意識してください。
- 感謝の気持ちを伝える(例:「短い間でしたが、学ぶことが多く感謝しています」)
- 辞めたい理由を簡潔に、ネガティブすぎないように説明
- 退職希望日を明確に伝える(例:「〇月〇日をもって退職したいと考えています」)
上司が忙しい場合は、事前にアポイントを取るか、落ち着いて話せるタイミングを見計らいましょう。
2. 退職届を提出する
口頭での相談後、正式に退職届を提出します。
退職届はシンプルに、以下の内容で作成しましょう。
退職届 〇〇株式会社 代表取締役社長 〇〇様 私、〇〇(氏名)は、一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたします。 〇年〇月〇日 〇〇(氏名)
退職届は手書きでもパソコン作成でも問題ありませんが、企業によっては指定のフォーマットがある場合も。
事前に人事部に確認しましょう。提出時は封筒に入れ、丁寧に渡すのがマナーです。
3. 引き継ぎを丁寧に行う
試用期間中でも、担当していた業務の引き継ぎは丁寧に行いましょう。
以下のポイントを意識してください。
- 業務内容や進捗をまとめた引き継ぎ資料を作成
- 後任者や上司に口頭で説明
- ファイルやデータの整理を行い、共有フォルダに保存
引き継ぎがスムーズだと、職場に良い印象を残せ、次の転職活動でのリファレンスチェックにも有利に働く可能性があります。

あなたの希望や強みを分析し、最適な転職エージェントを紹介!
\無料カウンセリングはコチラ/
オンライン面談無料、20代の転職活動を最適なエージェントで解決!
試用期間中に辞める際の注意点
試用期間中の退職は比較的スムーズに進むことが多いですが、以下の点に注意して進めましょう。
1. 感情的にならない
職場の不満やストレスが原因で辞める場合でも、感情的な態度や批判的な発言は避けましょう。
退職時の印象は、将来の転職活動で前の職場に問い合わせがあった場合に影響する可能性があります。
冷静かつプロフェッショナルな対応を心がけてください。
2. 次のキャリアプランを考える
辞めた後の生活や仕事の計画を立てておくことが重要です。
次の仕事が決まっていない場合、経済的な不安や焦りにつながることもあります。
試用期間中に転職活動を並行して進めるか、少なくとも退職後の生活費やスケジュールを計画しておきましょう。
3. 社会保険や税金の確認
退職後、健康保険や年金の手続きが必要です。以下の選択肢を検討しましょう。
- 国民健康保険に加入:市区町村の役所で手続き。保険料は前年の収入に応じる。
- 前の職場の健康保険を任意継続:退職後2年間、前の職場の健康保険を継続可能。ただし、保険料は全額自己負担。
- 国民年金の加入手続き:退職後、国民年金に切り替える必要がある。役所で手続き可能。
また、源泉徴収票を受け取り、次の職場で提出できるよう準備してください。
年末調整や確定申告に必要です。
4. 退職理由をどう伝えるか
退職理由を聞かれた際、ネガティブな理由(例:「上司が嫌い」「給料が安い」)は避け、前向きな表現を心がけましょう。
以下は例です。
- 「自分のキャリア目標に合った仕事を探したい」
- 「新たな挑戦をしたいと考えた」
- 「プライベートな事情で働き方を変えたい」
正直さは大切ですが、職場に不満があっても穏やかに伝えることで、円満退職につながります。
試用期間中に辞めたいと思ったときのメンタルケア
辞めたいと思うことは、精神的に大きな負担になります。
以下の方法でメンタルケアを行い、冷静な判断を心がけましょう。
1. 信頼できる人に相談する
友人、家族、信頼できる同僚に悩みを話すことで、気持ちが整理されます。
客観的な意見を聞くことで、新たな視点を得られることもあります。
もし身近に相談相手がいない場合、キャリアカウンセラーやメンタルヘルスの専門家に相談するのもおすすめです。
2. ストレス発散の時間を確保
運動、趣味、瞑想、旅行など、自分をリフレッシュさせる時間を作りましょう。
ストレスを溜め込むと、冷静な判断が難しくなります。
例えば、週末に散歩やヨガをする、好きな本を読むなど、小さなリフレッシュでも効果的です。
3. 自己肯定感を高める
「辞めたいと思う自分はダメな人間だ」と自己否定に陥りがちですが、試用期間中に辞めることは決して失敗ではありません。
自分に合った環境や仕事を見つけるための大切な一歩です。
過去の成功体験や自分の強みを振り返り、自信を取り戻しましょう。
試用期間中の退職を前向きな一歩にするために
試用期間中に辞めたいと感じるのは、キャリアや人生を見つめ直すチャンスでもあります。
無理に続けることでストレスを溜めるよりも、自分に合った環境や仕事を探す方が長期的にプラスになることも多いです。
以下のポイントを参考に、次のステップに進みましょう。
1. 転職活動を始める
退職を決めたら、早めに転職活動を始めましょう。
以下の方法が効果的です。
- 転職エージェントを活用:リクナビNEXT、doda、マイナビなどのエージェントに登録し、専門家のサポートを受ける。
- 求人サイトをチェック:Indeedやエン転職で、自分の希望条件に合った求人を探す。
- 自己PRを磨く:試用期間中の経験を活かし、履歴書や面接での自己PRを準備。
試用期間中の短期間の退職を履歴書に記載するか迷う場合、「職歴として短すぎる場合は省略可能」と考える企業もありますが、正直に伝える方が信頼感につながります。
その際、「自分に合った環境で長期的に働きたいと考えた」と前向きに説明しましょう。
2. 企業研究を徹底する
今回の経験を活かし、次の職場では企業文化や労働条件を事前にしっかり確認しましょう。
以下のポイントをチェックしてください。
- 求人票の詳細(業務内容、給与、労働時間)
- 企業の口コミ(OpenWorkやVorkersで確認)
- 面接時に質問(例:「試用期間中の業務内容は?」「職場の雰囲気は?」)
面接時に積極的に質問することで、入社後のミスマッチを減らせます。

あなたの希望や強みを分析し、最適な転職エージェントを紹介!
\無料カウンセリングはコチラ/
オンライン面談無料、20代の転職活動を最適なエージェントで解決!
まとめ:試用期間中の退職は自分を大切にする選択
試用期間中に辞めたいと思うのは、決して失敗や弱さではありません。
自分に合わない環境を早めに見極め、次のステップに進むための勇気ある決断です。
この記事で紹介した理由の整理、法律の知識、手続きの流れ、注意点、メンタルケアの方法を参考に、ストレスなく円満退職を目指してください。
退職を決めたら、引き継ぎを丁寧に行い、次のキャリアに向けて前向きに準備を進めましょう。
転職活動では、今回の経験を活かし、自分に合った職場を見つけることが大切です。
もし具体的なアドバイスやサポートが必要なら、転職エージェントやキャリアカウンセラーに相談するのもおすすめです。
あなたが自分らしく働ける場所をきっと見つけられるはずです!



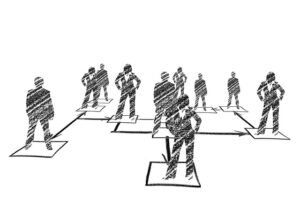






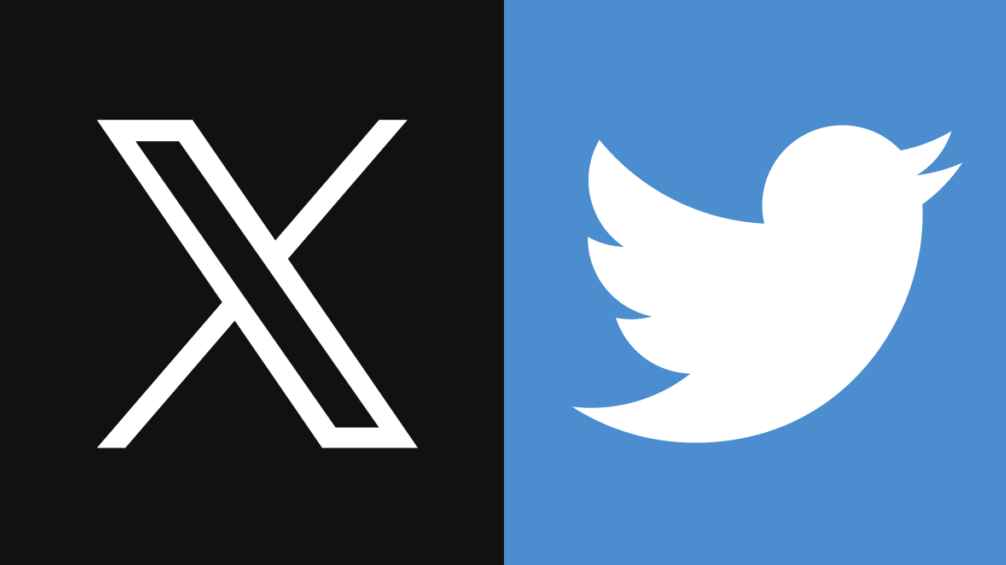

コメントを残す